Category: Creativity クリエイティブ
-
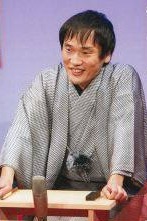
笑福亭里光師匠のこと
落語家の笑福亭里光師匠は中学時代の同級生です。同じクラスのときはけっこう仲良くしていて、同じ部活に入って、同じ日にその部活を一緒に辞めに行った間柄でした。中学時代から落語をやるのが趣味で、学校のイベントなどで高座を設けてもらって一席やったりすることがあって、それがただの趣味の域を超えてけっこう上手かったんですね。
-
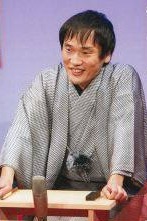
Shofukutei Riko
Shofukutei Riko (笑福亭里光) is a professional rakugo artist who speaks Kansai-dialect rakugo stories. Rakugo is, as written in Wikipedia, a form of Japanese verbal entertainment where the lone storyteller sits on stage and depicts a long and complicated comical (or sometimes sentimental) story using only a paper fan and a small cloth as props. He was…
-
CATVをデジタル化
うちのCATV(JCOM)をアナログからデジタルにアップグレードした。 特にこれといって動機があったわけではなかったのだが、地デジブームでもあるし、2011年にはアナログ放送が全廃されてすべてデジタル化されるということもあるので、時代を先取りという意味で、デジタル化してみた。 切り替え工事自体は特段難しいわけでもなく、業者の人が来てセットトップボックスを交換し、配線し直して初期設定するというだけで、ものの1時間で済む程度の作業。これで、チャンネル数もアナログ時代より格段に増え、海外の映画やニュース番組、そしてペイ・パー・ビューの番組なども見られるようになり、またCATV局~ユーザ間でのインタラクティブな操作も可能となって、非常に充実したテレビライフが送れるようになった。気に入った番組をどんどんDVDに落とし込んで、コレクションを充実させられる、と期待していたのだが、甘かった。 HDDレコーダーに録画した番組は、一世代しかコピーできないのである。
-
続・ものを書くこと
NHKのBS2「週刊ブックレビュー」に、先日芥川賞を受賞した金原ひとみさんがゲストで対談していた。 NHKなので、あまり過激なことは言わず、多分にぶりっ子風の話し方をしていたが、対談全体を通して感じたのは、彼女もまた、「ものを書く」ということに魅せられた一人のようだ、ということだ。 こんなところでちょろちょろっとゴミみたいな文章を書き散らしているだけの僕が語るのもおこがましいのだが、ものを書くというのは、以前もこのブログで触れたように、一番手っ取り早くコストのかからない表現手段で、わりと誰にでも始めやすい。金原さんも、たまたま書くことが好きで小説やら短編やらを書くようになり、そこへ天性の才能がジャストフィットして、ついには大きな花となって開いたということだろう。「一生、書くことはやめないと思います」と語る彼女。人生としてはこれにまさる幸せはあるまい。 あまり若いうちから「物書き」をやるのはよくない、という意見もある。書くという仕事は最高に集中力を要求される職業で、その集中力を何ヶ月、何年という長期間、維持しなければならない。そうやってずっと集中状態で執筆に専念し、やっと作品を書き上げたあと、それまで出っぱなしだったアドレナリンがおさまらずに、ハイなままになってしまって、それを自分でコントロールできなくなってしまうことがあるらしい。そうなると、精神的なバランスが崩れてしまう。 僕もこのブログを夜中に書いていると、だんだん目がさえてきて書き終わった後も眠れなくなったりすることがある。たかだか数千字程度の短い文章を書いてさえもそうなのだから、ましてや長編小説など書く作家さんなどは、こんなものではなかろう。 そして、集中状態をリセットするために、アルコールを入れたり、クスリに頼ったりすることになり、それでもおさまらないと、いよいよ心の病を発することになる。そういえば、昔から作家といわれる人の自殺率は半端じゃない。 金原さんは、「書くことは小さいときから自分の生活の一部で、いわば日課のようなものだ」とさらっと語る。自分の「こころ」に自分で折り合いがつけられるというのは、相当の精神力の持ち主だと感心させられる。 彼女は小学生時代に不登校に陥り、そのあとは歌舞伎町を徘徊してパチスロに明け暮れ、配管工の彼氏と同棲して今に至るとのこと。「2ちゃんねる」風に言えばまさに絵に描いたような「ドキュン」と言えるのかもしれないが、物書きというものは大体において破天荒なものである。僕のようにどちらかというとボンボン育ちで、レールの上をある程度外れずに生きてきたような人種からすると、彼女たちのような自由な生き方がある意味、羨ましかったりすることもある。 「がんばって生きてる人って何か見てて笑っちゃうし、何でも流せる人っていいなあ……」と悪びれず言ってしまう態度に反感を持つ向きもあるようだが、若いからこそ許される、20歳の無邪気な発言と鷹揚に構えたい。これから、密度の濃い体験をいろいろ重ねて、人間としての深みの備わった作品を何十作も出してほしい。 Technoratiタグ: 本 | 金原ひとみ |
-
ものを書くこと
僕にとって、ものを書くということは、他のどんな表現手段――音楽や、絵画や、演劇や、映画などといった手段――よりも、一番手っ取り早く、easy-to-doな自己表現手段だと思う。何よりおカネがかからない。特にWebというメディアでは、最低限の機材とソフトウェアさえあれば、それがいともたやすく実現できてしまう。それに、口で言うとリアルタイムでやり直しがきかないことでも、書くのであれば、あとで推敲したり、編集したり、削除したりすることができる。 僕はいままで、ホームページというメディアで情報発信してきた。それはWeb黎明期には個人の情報発信手段としては絶大かつ画期的なものであった。しかしWebという表現手段が普及し、Webにまつわる技術が長足の進歩を遂げるようになると、凝ったサイトを作るのにもお金をかけて稼動や工数を見積もり、プロジェクトチーム単位で動かさなければならなくなった。 それでは、お金も何もない一個人は、どうすればいいのか。 そこで、ブログという手段がここ1年ほどの間に急に注目を浴びるようになった。僕も今まではあまり知らなかったのだが、アメリカではブログが個人の情報発信の標準的なツールになっているらしい。ブログツールの日本語化の進歩に伴って、日本でも最近、にわかに脚光を浴びるようになっている。 新しいもの好きの僕としては、使える技術は何でも使ってみることを信条としていることもあるし、こういう流れに遅れるわけにはいかない。ということで、ブログがどんなものか、にわか勉強を始めたのが今年に入ってすぐ。それから数週間、解説書と首っぴきになりながらようやく開設にこぎつけた。 「ものを書く技術」を磨きたい――その気持ちを大事にして、毎日でも何か書けるように、ブログをいろいろ活用してみようと思う。